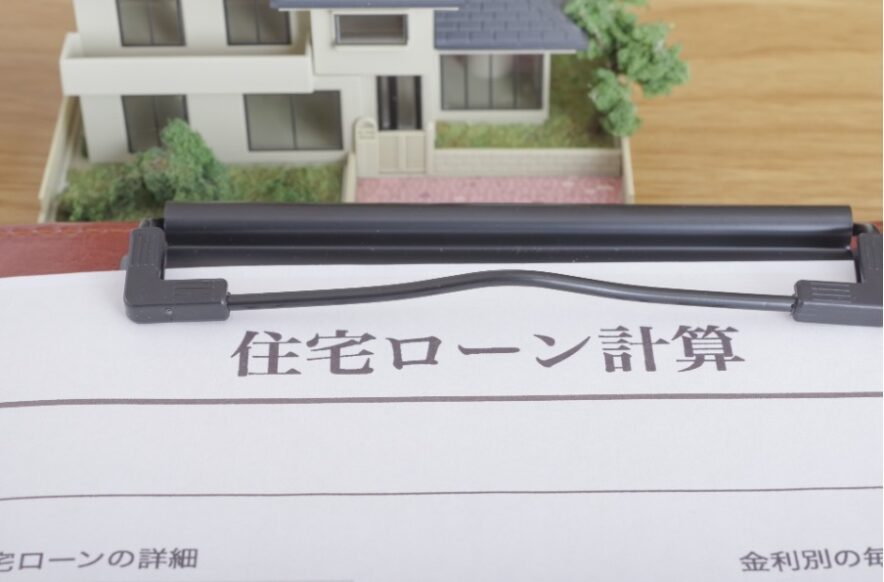「毎月かかる住宅ローン以外に、光熱費や税金、メンテナンス費用まで…家を持つって本当にお金がかかる!」そう感じていませんか?
ランニングコストは、住宅を持つ上で避けて通れないものです。しかし、工夫次第でこのランニングコストを大幅に抑えることが可能になるのです。 初期費用を抑えることばかりに目が行きがちですが、長い目で見たときの生活の豊かさを左右するのは、まさにこのランニングコストと言えるでしょう。
本記事では、ランニングコストを抑えるための具体的な方法をご紹介し、家計に優しい、そして地球にも優しい理想の住まいづくりを実現する方法を探っていきます。
Contents
住宅のランニングコストとは?

住宅を維持するには、さまざまな費用がかかります。それらの費用をまとめて「ランニングコスト」といいます。ここでは、ランニングコストの定義や具体例について詳しく解説します。
ランニングコストの定義
住宅のランニングコストとは、家を維持するために継続的にかかる費用のことです。家を買う時の費用(イニシャルコスト)は一度きりですが、ランニングコストは住み続ける限り発生し続けます。
具体的には、固定資産税・都市計画税などの税金、火災保険などの保険料、家の修理費用、電気・ガス・水道などの光熱費、住宅ローンを組んでいる場合はその返済などが挙げられます。
ランニングコストは住宅の広さや設備、家族構成、ライフスタイルによって大きく変わるため、事前にしっかりと把握しておくことが大切です。
ランニングコストの具体例
ランニングコストには、以下の費用が含まれます。
- 毎月の光熱費
- メンテナンス費用
- セキュリティ費用
- 火災保険料・地震保険料
- 税金(固定資産税や都市計画税)
それぞれの内容について詳しく見てみましょう。
毎月の光熱費
光熱費は、住宅の維持に欠かせないランニングコストの一つです。総務省統計局が発表した「家計調査 2023(令和5年)」を見ると、二人以上の世帯の月平均23,855円の光熱費がかかっています。内訳は以下の通りです。
【光熱費の内訳】
| 費目 | 金額 |
| 電気代 | 12,265円 |
| ガス代 | 5,209円 |
| 上下水道料 | 5,106円 |
| その他 | 1,275円 |
| 合計 | 23,855円 |
出典:総務省統計局「家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要」
季節による使用量の変動が大きいのが特徴で、例えば、夏の暑い日に欠かせないエアコンや、冬の寒さをしのぐための暖房器具は、電気を多く消費します。また、料理に使うガスコンロや、毎日入るお風呂に使うお湯にも、ガスや水道料金が発生します。
メンテナンス費用のつみたて
住宅のメンテナンス費用は、建物を長持ちさせるために欠かせない支出です。特に外壁や屋根は、雨風にさらされるため10年程度で補修が必要となります。具体的には、屋根の一部修理で10万円程度、外壁の塗り替えで50万円前後、屋根の葺き替えでは100万円以上かかることもあります。
給湯器やエアコンといった住宅設備も、10年前後で交換が必要になる可能性があります。このように、老朽化に伴う住宅のメンテナンス費用は確実に発生するため、トラブルがなかったとしても、毎月積み立てておく必要があるのです。
セキュリティ費用
住宅のランニングコストには、セキュリティ費用も含まれます。最近では、24時間365日体制で見守るホームセキュリティサービスが人気です。例えば、ALSOKやセコムなどの警備会社と契約すると、月々5,000円から1万円程度の費用で、緊急時には警備員が駆けつけてくれます。
火災発生時のセンサーによる通報や、外出時の不正侵入対策など、安心を「買う」という意識が広がっています。初期費用がかかる場合もありますが、毎月のランニングコストとして、セキュリティ費用を考慮する必要があります。
火災保険料・地震保険料
火災保険料や地震保険料も、住宅を維持するうえで必要なランニングコストです。火災保険は、火災だけでなく、台風による風災や水災、落雷、雪災など、幅広い自然災害をカバーします。例えば、台風で屋根が破損した場合でも、火災保険で修理費用が補償されます。
一方、地震保険は地震による火災や損壊を補償します。地震保険は火災保険とセットで加入するのが一般的です。地震による被害は甚大になりがちなので、地震保険への加入は重要です。火災保険料と地震保険料をあわせて、年間数万円程度のコストを見込んでおくべきでしょう。
税金(固定資産税や都市計画税)
住宅を所有していると、土地や建物にかかる固定資産税や都市計画税を支払わなければなりません。
固定資産税は、土地や建物といった固定資産を所有していることに対して市区町村に納める税金で、固定資産税評価額に1.4%の税率を掛けて計算されます。都市計画税は、都市計画区域内の住宅に対して課せられる税金で、固定資産税と合わせて支払います。
ただし、住宅用地には特例措置があり、200平方メートル以下の小規模住宅用地では、固定資産税が評価額の6分の1に軽減されます。また、新築住宅では3年間(認定長期優良住宅は5年間)、固定資産税が2分の1に軽減される制度もあります。
ランニングコストを抑えるにはどうすればいい?

ランニングコストを抑えるには、建物自体の性能向上や設備の選び方、生活上の工夫など、様々な方法があります。家づくりの段階から計画的に取り組むことで、長期的な視点での家計の負担を軽減できます。
建物の断熱性能や気密性能を高める
建物の断熱性能と気密性能を高めることは、住宅の光熱費を大きく削減できる重要な要素です。例えば、夏の強い日差しも厚い断熱材が遮り、冬の冷たい空気も高気密な構造がシャットアウトするため、冷暖房効率が格段に向上します。冷暖房の使用頻度が減ることで、電気代やガス代などの光熱費を大幅に削減できます。
断熱性能を高めるには、壁や天井、床に断熱材を十分に施工し、窓には複層ガラスやLow-E複層ガラスを採用します。また、玄関ドアも断熱性の高い製品を選択することで、熱の出入りを最小限に抑えられます。
高気密化により室内の温度むらが解消され、結露の発生も防げるため、建物の耐久性が向上し、メンテナンス費用も抑えられます。初期投資は必要ですが、長期的に見ると大きな経済的メリットがあるといえるでしょう。
省エネ性能が高い冷暖房器具や給湯機を導入する
省エネ性能が高い冷暖房器具や給湯機を導入することでも、ランニングコストを抑制できます。最新の冷暖房器具や給湯機は、省エネ性能が格段に向上しているからです。
例えば、従来の電気給湯器やガス給湯器と比べて、エコキュートは空気の熱を利用してお湯を沸かすため、電気代を大幅に節約できます。また、高断熱住宅に床暖房を導入すれば、部屋全体を優しく暖めることができ、エアコンとの併用で更に効率的です。
LED照明への切り替えも効果的です。初期費用はかかりますが、ランニングコストを抑え、快適な暮らしを実現できます。毎日の生活で賢くエネルギーを選び、快適でお得な暮らしを手に入れられるでしょう。
屋根の軒を深くする
軒を深くすることで、夏場は強い日差しを遮り室内温度の上昇を抑制できるため、エアコンの使用を抑えられます。また、外壁が雨風や紫外線から守られることで劣化が抑えられ、塗装などのメンテナンス費用を節約できます。冬場は太陽高度が低いため日差しを遮ることなく室内に取り入れられ、暖房費の削減にも貢献します。
このように、軒を深くすることで光熱費やメンテナンス費用を抑え、ランニングコストを削減できます。
水回りでの節水を徹底する
毎日の生活で欠かせない水回り。実は、少しの工夫でランニングコストを抑えられます。例えば、トイレは従来型から節水型へ交換するだけで、大幅なコストダウンが見込めます。
また、節水シャワーヘッドは水圧を調整し少ない水量でも快適なシャワーを実現、水道代だけでなくガス代も削減できます。食器洗い乾燥機も、手洗いと比べて使用水量が少なく、節水に貢献します。
間取りを工夫する
住宅のランニングコストを抑えるためには、間取りの工夫が重要です。部屋数を必要最小限に抑え、シンプルな間取りにすることで、建築費用だけでなく、メンテナンスのための維持管理費用も削減できます。
また、凹凸の少ない総二階の家は、外壁面積が少なくなるため断熱性能が上がり、冷暖房費を抑えられます。さらに、メンテナンスが必要な外壁面積も減るため、塗り替えなどの費用も軽減できます。
日当たりや風通しにも配慮が必要です。南面に大きな窓を設置し、夏場の強い日差しを考慮して適切な長さの軒を設けます。反対に西日の強い西側の窓は小さくするなど、自然の力を活用することで、エアコンの使用を抑え、光熱費の削減につながります。
太陽光発電や蓄電池を導入する
太陽光発電と蓄電池を導入すれば、自宅で発電した電気を使えるので、電気代を大幅に節約できます。例えば、日中の太陽光発電で作った電気を冷蔵庫やエアコンに使い、余った電力は電力会社に売ることも可能です。
さらに、蓄電池があれば、夜間や曇りの日でも発電した電気を使えるため、より経済的です。日中に蓄電池にためた電気で、夜の照明やテレビを動かすことができます。また、災害時には非常用の電力としても利用可能です。
初期費用はかかりますが、長期的に見ると電気代を抑えられ、経済的なメリットが大きいです。さらに、環境にも優しく、省エネにも貢献できます。導入を検討する際は、補助金制度も活用し、ランニングコストと合わせて比較検討しましょう。
まとめ
今回は住宅のランニングコストの定義や具体例、コストを抑えるための6つの方法について解説してきました。
住宅のランニングコストには、光熱費、メンテナンス費用、セキュリティ費用、保険料、税金などがあります。これらを抑えるには、建物の断熱性能や気密性能の向上、省エネ設備の導入、適切な間取り設計が効果的です。 また、太陽光発電や蓄電池の導入、水回りでの節水など、日常的な工夫も重要です。初期投資は必要ですが、長期的には家計の負担を大きく軽減できます。
ぜひ一度オンラインでできる無料相談にお越しくださいませ。