家の新築には大きなお金が動きます。
一般的には住宅ローンを利用しますが、国土交通省・環境省・経済産業省が連携を取った住宅補助金を利用できるのをご存じでしょうか。
利用するためには、補助金対象住宅の条件を満たす必要があります。
2025年も住宅補助金の募集が始まり、多くの方の募集が見込まれるでしょう。
住宅補助金は毎年予算と応募期間が定められており、予算に達してしまうと期間内であっても終了するケースがあります。
本記事では補助金制度に申請し確実に受け取るために、2025年度住宅補助金をご案内しメリット・デメリットと申請方法を解説します。
Contents
2025年住宅補助金「子育てグリーン住宅支援事業」とは?
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた、2025年の住宅補助金制度です。
内容としては、「ZEH基準の省エネルギー性能確保」の義務化を視野に入れ、エネルギー価格や物価高騰の影響を受けやすい世帯を中心に支援します。
2024年度に実施された「子育てエコホーム支援事業」は、子育て世帯、若者世帯が高性能
住宅を建てるための支援でした。
2025年の子育てグリーン住宅支援事業はGX志向を新設し、住宅性能の基準や補助額がアップしています。
子育て世帯・若者世帯だけでなく、幅広い世帯に対して省エネ住宅取得のための補助金を支給する取り組みです。
新築住宅の補助金概要
| 補助金対象住宅 | 補助金額 | 古家の除去を行う場合の加算額 |
| GX志向 | 160万円 | なし |
| 長期優良 | 80万円 | 20万 |
| ZEH水準 | 40万円 | 20万 |
子育てグリーン住宅支援事業は、省エネ住宅を新築か購入した世帯に対して補助金を交付する制度で、住宅の性能によって金額が異なります。
2024年の補助金制度では、子育て世帯と若夫婦世帯のみが対象となっていましたが、GX志向型住宅が追加になったことで対象世帯が幅広くなりました。
GX志向型住宅は、長期優良住宅やZEH水準住宅よりも補助金額が大きくなっているのが特徴です。
補助金額が大きいのは、建築や設備など初期費用が高額であることを示しています。
新しい制度のため、施工会社が知識や技術力を持っているのかも、確認しなければなりません。
新技術を取り入れた建築ができる会社は少ないですし、確かな技術がなければ完全な省エネ住宅の建築は難しいでしょう。
それぞれの補助金対象住宅の違い

高性能なZEH住宅に対してZEH水準は、断熱等性能等級5・一次エネルギー消費量削減・等級6を同時に達成することが目的です。
換気システムの導入や高性能な断熱材の利用は必須ですが、太陽光発電システムなど再生可能エネルギー導入までは至らない点が違います。
長期優良住宅は、スクラップ&ビルド型社会を見直し、長期に住み続けられる優良な住宅を建築することです。
建物の劣化対策として、土台や基礎などの構造躯体には劣化しにくい材質を使い、土台や地盤について防蟻処理などです。
また耐震性や防火性の高さにも着目し、エコ設備よりも「長く住み続ける」家にすることを目的としています。
一次エネルギー削減の決まりはなく、税制優遇が受けられるのが特徴です。
GX志向型住宅は、省エネ・再生可能エネルギーの活用とCO2削減の取り組みが強調されています。
長期優良住宅よりも一次エネルギーの消費量15%減が定められるなど、非常に厳しい基準となっています。
断熱性の向上はもちろんですが、再エネ設備の設置やエコキュートや省エネ効果のある冷暖房・照明など高効率な設備投資が必要です。
長期優良住宅やZEH水準は、建て替えやリフォームにも補助金が支給されますが、GX志向型住宅は新築のみが対象となっているのが特徴です。
3つの補助金対象住宅は、断熱等級や一次エネルギー消費量の削減する点については目的が同じですが、再生エネルギーについての定めや制限に違いがあります。
GX志向
| 省エネ性能 | 一般地域 | 寒冷地及び低日斜地域 | 多雪地域及び都市部狭小地域 |
| 断熱等性能等級 | 等級6以上 | 等級6以上 | 等級6以上 |
| 再生可能エネルギーを除く 一次エネルギー消費量 | 35%以上 | 35%以上 | 35%以上 |
| 再生可能エネルギーを含む 一次エネルギー消費量 | 100%以上 | 75%以上 | 要件なし |
| 高度エネルギーマネージメントの導入 | ECHONET Lite AIF仕様対応コントローラーとして「一般社団法人エコーネットコンソーシアム」掲載製品を設置 | ECHONET Lite AIF仕様対応コントローラーとして「一般社団法人エコーネットコンソーシアム」掲載製品を設置 | ECHONET Lite AIF仕様対応コントローラーとして「一般社団法人エコーネットコンソーシアム」掲載製品を設置 |
GX志向とは、子育てグリーン住宅支援事業で新設された、省エネ性能の向上を目指す新たな基準です。
持続可能な高水準の省エネ住宅を支援する取り組みで、高断熱性能以外にもエコキュートや
太陽光発電などの一次エネルギー導入を前提としています。
子育てグリーン住宅支援事業の中でも非常に厳しいですが、光熱費の大幅な削減が可能になり、すべての世帯を対象としているのが特徴です。
長期優良住宅認定も同時に取得するため、住宅の資産価値向上にも高い効果をもたらします。
断熱等性能等級「6以上」は、快適性と省エネ性を両立したZEHを超える性能でもあります。
季節を問わず快適に暮らせるだけでなく、ヒートショックのリスクも低減され、結露予防にもなるためハウスダストやカビなどからも家族を守ることができます。
高断熱性能は防音効果にも優れており、騒音が室内に響くことがなくなりますから、快適な生活が送れるのがメリットです。
省エネ性能に優れた家電設備やハイブリッド給湯器・照明器具などを使い、住宅での消費エネルギー量の削減を目指します。
GX志向では、太陽光発電などで生み出されたエネルギーを使わずに、一次エネルギー消費量を35%削減します。
今までの省エネ住宅との違いは、エネルギーを自給自足し、脱酸素社会にも大きく貢献できるのが魅力です。
長期優良
| 劣化対策 | 劣化対策等級3 構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)に応じた基準 |
| 耐震性 | 耐震等級2以上または免震建築物など 耐震等級2は建築基準法の耐震等級1の1.25倍 |
| 省エネルギー性 | 断熱等性能等級5・ 一次エネルギー消費量等級6 |
| 居住環境 | 地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画などに配慮されていること ※申請先の所管行政庁に確認 |
| 維持保全企画 | 定期的な点検、補修等に関する計画が策定されていること |
| 住戸面積 | 一戸建ては75㎡以上であること 一つのフロアの床面積が40㎡以上あること |
| 維持管理や更新の容易性 | 維持管理対策等級(専用配管)等級3 |
| 災害への配慮 | 災害リスクに合わせた処置がされていること |
長期優良とは、平成21年スタートの「長期優良住宅認定制度」の基準をクリアする条件です。
今までのように、古い家は建て替えて住むのではなく、資産価値を保ちながら長く安心して快適に暮らせる家を目指します。
具体的には、耐震性・耐久性や省エネ性能に優れた、高性能住宅を指しています。
長期優良の魅力は、安心して長く住み続けられるだけでなく、税制にメリットがある点です。
新築住宅を購入する際には住宅ローンを利用しますが、住宅ローン減税が適用され13年間の控除限度額合計は最大455万円になります。
登録免許税の税率は一般住宅が0.15%に対して長期優良住宅は0.1%ですし、固定資産税は減税措置の適用期間が延長されます。
フラット35Sとフラット35の併用によって、初回から5年間は0 75%の金利引下げが受けられるだけでなく、フラット50も利用可能です。
地震保険料は耐震等級に応じた割引率が適用になるため、長期優良認定を受けていれば保険料を抑えられるでしょう。
ZEH水準
| 断熱性能 | 耐熱等級5 高断熱材・高断熱サッシを利用し断熱性能を高めます。 |
| 高効率設備 | エコキュート・ハイブリッド給湯器の導入 LED照明、省エネエアコンなど |
ZEH水準とは断熱等性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上の高省エネ基準で、ZEHとは違い太陽光発電は必須としていません。
高性能な断熱材やサッシ窓・玄関などを設置し強化外皮基準に適合させ、換気システムや太陽光発電システムなどを導入します。
年間の室温が一定で、夏は涼しく冬は暖かいため、ヒートテックなどの健康被害リスク対策にも有効であることがわかっています。
ZEH水準は新築住宅の最低基準となる見込みであり、今後は高い省エネ基準の住宅によって脱酸素社会が実現されていくでしょう。
ZEH水準の要件は、太陽光発電などの再エネ設備を導入する必要がないため、省エネ補助金の中でも申請しやすくなっています。
太陽光発電システムなど高額な設備を導入しなくても、省エネ基準を満たしていれば補助金の対象となるため、費用を抑えられるのがメリットです。
2025年の新築住宅補助金の変更点

2023年に引き続き「2024子育てエコホーム支援事業」、そして「子育てグリーン住宅支援事業」の募集が始まりました。
カーボンニュートラルに向けた省エネ住宅の推進にむけて、新たな省エネ基準が加わり補助金額も大幅に増額されています。
ここからは2025年度の新築住宅補助金の変更点のなかでも、特に注目すべき2点を紹介します。
GX志向型住宅
2025年の新築住宅補助金で大きく変更があったのは、新設された「GX志向型住宅」の存在です。
脱炭素社会の実現に向け、ZEH水準よりも高い省エネ性能を基準としました。
今までは「子育て世帯」「若者夫婦世帯」が補助金対象者でしたが、GX志向型住宅は全世帯が対象となっています。
カーボンニュートラル実現に向け、省エネ基準をZEH水準に引き上げるための施策で、補助金額は160万円と過去最高額です。
高断熱・高気密はもちろんですが、省エネ設備は導入するだけでなく厳しい基準が設けられました。
高度エネルギーマネージメントの導入が必須で、ECHONET Lite AIF仕様に対応するコントローラーとして、一般社団法人エコーネットコンソーシアムのホームページ掲載製品の設置が必須となっています。
認証を受けていない製品は補助対象とならないため、注意が必要です。
建替加算とZEH水準住宅の低減
GX志向型住宅が新設され、ZEH水準住宅及び長期優良住宅の補助金額は以下の通りに変更されました。
| 補助金対象住宅 | 2025年 | 2024年 |
| ZEH水準 | 40万 | 80万 |
| 長期優良住宅 | 80万 | 100万円 |
ZEH水準住宅の補助金が大幅に低減されたのは、新設のGX志向型住宅の施策であると考えられます。
建替加算される金額は20万円、ZEH水準へ建て替えすると補助金は60万円に、長期優良住宅は100万円の支給です。
近年は物価の高騰やガソリン・電気料金の値上げが続いており、今後は光熱費の節約が課題となっていくでしょう。
初期投資は高額になりますが、断熱性能や省エネ設備によって光熱費を抑えられるだけでなく、長期的に快適な生活が送れます。
住宅の建て替えを検討している方には、大きな金額となりますから、補助金を活用してみてください。
補助金を受けるメリット・デメリット

省エネ住宅だけでなく、省エネ設備の導入にも利用できる補助金も増えたことで話題になりました。
補助金を利用すれば、マイホームを手に入れるための経済的な負担を軽減できます。
初期費用はかかりますが、将来的な資産価値や光熱費の削減などのメリットが得られるでしょう。
ここでは、経済的負担の軽減以外にどのようなメリットがあるのか、デメリットについても解説します。
メリット
省エネ住宅は設備にも費用がかかるため、マイホーム購入を検討していても予算オーバーしてしまうケースが多くみられます。
気密・断熱性能が高い家は、外的な刺激にも強く室内の温度を一定に保てることからも老朽化の進みがゆっくりです。
省エネ住宅は快適性の高い家を長く保つための工夫が凝らされています。
補助金を利用すれば、対象住宅によっては税金の優遇措置が受けられますし、光熱費の節約に住宅維持費を節約できます。
デメリット
金銭的な負担を軽減できる補助金ですが、デメリットがないわけではありません。
省エネ性能が高くなれば、建築費用はもちろんですが、設備にも費用がかかります。
GX志向型住宅の場合、断熱性能だけでなく第一エネルギー設備の導入も必要となるため、
建築・設備費用を合わせると予算オーバーになるケースも少なくありません。
不備があり審査を通過できずに、諦めなければならない方もいるでしょう。
高額な補助金だけに、審査が厳しく受け取れない場合もあります。
申請の方法と必要な書類は
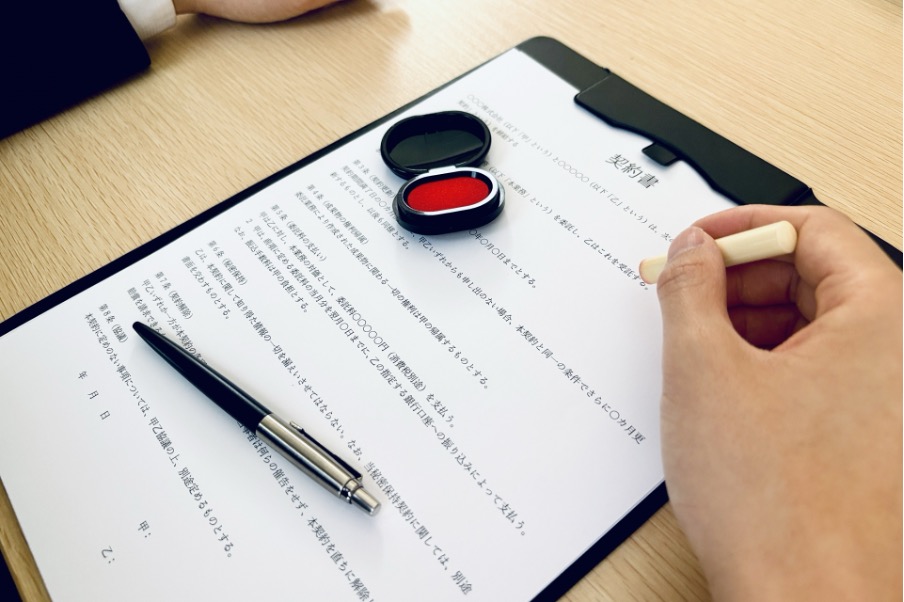
マイホーム購入に使える補助金制度はいくつかあります。
自分が対象となる補助金を探したら、内容を確認し必要な書類を集めて申請しましょう。
ここでは、補助金の申請方法と提出に必要な書類について解説します。
申請方法
一般的に申請書は申込本人が必要な書類を集めて申請しますが、住宅補助金に関してはハウスメーカーや工務店などが代理で行います。
省エネ住宅を建築すると言って、お金だけを受け取ることがないように、施工会社が「省エネ住宅を建築します」という証明書が必要な書類です。
そのためには、施工会社に見積書を出してもらい、契約を結んで建築し証明書や写真を添付しなければならないからです。
省エネ住宅建築事例のある建築会社であれば、何度も申請をしてわかっていますからお任せするのがいいでしょう。
書類のほとんどは、建築会社が用意し提出するものです。
中途半端な書類や記載がわかりにくい、いいかげんなものは審査を通過しませんので、信頼できる建築会社を選ぶのもポイントになります。
必要な書類
申請したい補助金によって必要な書類は異なります。
自治体の助成金や補助金を申請する場合には、納税証明書などの提出が求められるケースもありますから注意しましょう。
書類が1枚欠けていても審査には通過することはできません。
申請者が省エネ住宅を新築する妥当性や実現性を判断するための基本情報であり、申請者が対象要件を満たしているか証明しなければなりません。
計画通りに新築できるかどうかは、見積書や契約書で判断されます。
補助金が不採択となる理由の一つとして記載漏れがある・書類が足りない・申請書のフォーマットの違いがあります。
マイホーム購入にむけてチャンスを逃さないために、書類準備は重要です。
補助金申請に必要な書類は建築会社が用意しますが、住宅所有者の証明書類も必要になるため事前に調べて用意しましよう。
申請までの流れ

申請書する補助金の要件に自分が当てはまるかを確認したら、準備を始めましょう。
ご自分が住んでいるエリア内で、評判の良い施工会社をピックアップします。
住宅を建築するエリアでの施工ができるのか、アフターサポートなどが受けられるかも確認しておくといいでしょう。
省エネ住宅の施工実績があるのか、施工会社のホームページで確認しておきます。
住宅省エネ2025キャンペーンのホームページでは、補助金の利用を相談できる業者・GX建築事業者の情報が掲載されています。
希望の工事が得意な会社を探したら、見積書を依頼し内容を確認し工事請負契約を結びましょう。
子育てグリーン住宅支援事業の場合は、「共同事業実施規約」も同時に締結してください。
工事が完了してから補助金を申請できますから、施工会社に交付申請予約の依頼をしておきましょう。
施工後は施工会社が必要書類をまとめ、補助金の交付申請が行われ審査結果を待ちます。
記載漏れや不備がない限りは交付されますから、自分が用意すべき書類は早めに用意しておいてください。
申請におけるスケジュール

2025子育てグリーン住宅支援事業は、新築補助とリフォーム補助があります。
新築住宅に係る補助金は、交付申請の受付が第Ⅰ期(5/14〜5/31)・第Ⅱ期(6/1〜6/30)・第Ⅲ期(7/1〜12/31)と分かれています。
第Ⅰ期は注文住宅のみの申請、分譲住宅は2025年5月30日・賃貸の新築は2025年6月30日から交付申請が可能です。
第Ⅲ期は2025子育てグリーン住宅支援事業最後の申請期間となり、申請予約は2025年11月14日まで、予算上限に達しなければ2025年12月31日まで申請できます。
リフォーム事業は、2024年11月22日以降に基礎工事に着手したものが対象工事です。
交付申請期間は2025年5月14日から申請を開始、予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)となっています。
交付申請の予約期間は、申請開始から予算上限に達するまでですが2025年11月14日で締め切られます。
申請スケジュールは新築・リフォームに大きな違いはありませんが、新築の工事着手は2024年11月22日以降であることが条件です。
それ以前に着工した住宅については、2025子育てグリーン住宅支援事業の対象案件にはなりませんのでご注意ください。
補助金を利用する際の4つの注意点

補助金を申請するには、いくつか気をつけておかなければならない注意点があります。
確実に受け取るために、ここでは4つのポイントについて触れています。
締め切りに間に合っているか
補助金は、毎年予算が組み替えられるため多少の余裕があるように思えますが、毎年申請期間前に締め切られています。
「締め切りまで時間がある」とのんびりしていると、予算上限に達してしまうため注意が必要です。
2025子育てグリーン住宅支援事業は、交付申請から3ヶ月間は「申請予約」によって予算の確保ができます。
期限日に間に合えばいいと工事を引き延ばしていると、締め切りが繰り上げられ申請できなくなります。
建築会社と工事請負契約を結ぶ際には、共同事業実施規約を同時に締結し交付申請予約の依頼をしておくと安心です。
住宅を建築する予定が決まったら、早めに申請予約をするか申請を進めてください。
対象条件に合っているか
補助金には補助対象住宅と補助対象者が決められています。
GX志向型住宅は、すべての世帯が補助対象者ですが、長期優良住宅・ZEH水準住宅は
子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれかです。
子育て世帯または若者夫婦世帯は、GX志向型住宅・長期優良住宅・ZEH水準住宅の対象ですが、それ以外の方はGX志向型住宅のみが対象となっています。
補助対象者の年齢や子育て世帯対象の子どもの年齢、住宅の立地条件や住宅の面積、性能確認など。細かく定められた要件に合っていなければ申請できません。
申請しても、要件を満たしていないと補助金は支払われませんので注意が必要です。
省エネ性能などの基準を満たした住宅の建築が条件のため、事前登録されていないハウスメーカーや工務店は利用できません。
注文住宅・分譲住宅共に省エネ性能基準をクリアした商品であることもポイントです。
補助金の対象要件を良く確認し、各事業登録がされている建築会社であるかを補助金ホームページで確認しましょう。
契約後に補助金が活用できない業者に依頼したと気づいた時には手遅れです。
すべての対象条件を確認し、スムーズに申請に進んでください。
書類不足や手続きミス
申請条件をクリアし、対象者であるにもかかわらず申請が通過しなかった方がいます。
補助金の支給は国土交通省・環境省が管轄のため、書類にミスがあったり不足していたりすると支給されません。
書類に不備がある・不足した場合には、期限付きでの再提出を求められるケースもあるようです。
しかしながら、期限を過ぎてからの提出や未提出は受け取り不可となり申請が却下されてしまいます。
補助金の申請は塗装会社が行いますが、補助対象者が用意する書類に不備がないのか不足がないかを確認してください。
申請予約を依頼した場合には、期限が切れていないのか、申請期限に間に合ったかなど建築会社に問い合わせることも忘れないようにします。
後から支給される
住宅補助金の支給は、建築会社からの実績報告書が提出された後に補助金額が決定し、支給額が決定します。
建築会社への最終支払い金額の一部に充当し還元されるため、それ以前の支払いはご自身での支払いが必要です。
工事請負契約時の手付金や工事着工金、上棟時の費用をあらかじめ用意し、支払い時に慌てないようにしてください。
子育てグリーン事業では補助金の交付額確定通知や振込明細は建築会社へ、申請者には振込確定通知が届きます。
建築会社は最終支払い金額に補助金を充当し残額を請求しますが、申請費用などが差し引かれるのか確認しておきましょう。
振込確定通知には補助金額が記載されていますから、紛失しないように契約書と一緒に保管がおすすめです。
補助金の活用は住宅メーカー選びが重要

住宅の省エネ基準義務化が進んだことで、今後はすべての新築は省エネ住宅になります。
補助金額も大幅にアップしたことで、新築住宅の購入がしやすくなってきました。
大きな金額が動く補助金を利用するためには、高い省エネ機能を持った住宅を建築できる会社選びが重要です。
住宅省エネポータルへの登録事業者であること、省エネ性能が高い住宅を建築できるノウハウがあることが挙げられます。
省エネ性能住宅の実績があり、お客様の意見を取り入れ満足度の高い提案ができるのかなども着目しましょう。
ご自身が住んでいるエリアで適切な業者がいるかどうかは、補助金の公式サイトで確認ができます。
理想の省エネ住宅を手に入れるために、補助金を上手に活用しましょう。
まとめ

私たちの生活が便利になればなるほどに、エネルギーを消費し地球温暖化が進んでいきました。
エネルギーを抑えることは、環境だけでなく暮らし全体が豊かになり生活を快適にしてくれます。
ECOを考える・省エネへの取り組みは特別なものではなく、私たちの生活に密着し家族の未来を明るく照らします。
これからの生活をより豊かにするためにも、住宅補助金を利用した家づくりをはじめましょう。
ご相談はコチラ!











